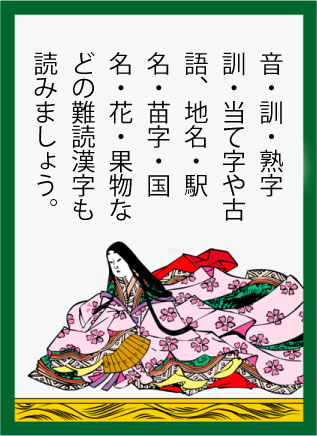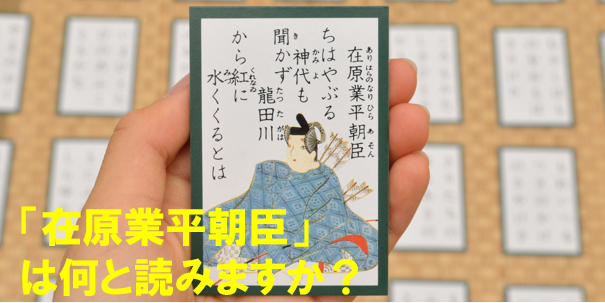本漢読検定の1級から2級は、原則として下記の「文化庁常用漢字表」と「文部科学省の用事用語例」から出題されます。3級から5級は、文部科学省の「学年別漢字配当表」を基に漢字を選択して出題されます。下記の3つの資料を確認されるとともに、各級の例題をしっかり学習して下さい。
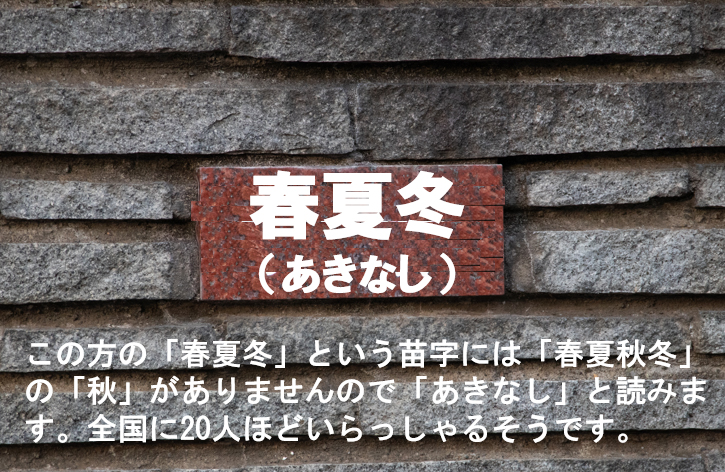
1.文化庁 常用漢字表
常用漢字は、日本で一般の社会生活において、現代の国語を書き表す際の漢字使用の目安として、内閣が告示している漢字です。現在では2136字が定められています。小学校、中学校、高校で習う漢字も数が決まっていて、小学校で1,026字、中学校で1,110字を学びます。高校卒業までにこの2,136字の音訓4,388(2,352音・2,036訓)を学習します。
2.文部科学省 学年別漢字配当表
この表は,常用漢字の音訓及び付表の語について,小学校,中学校及び高等学校等の学校段階ごとの割り振りを示すものである。平成3年に作成した「音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表」をもとに,平成23年に常用漢字表の改定に伴う一部補訂を行い,このたび、学年別漢字配当表の改定に伴う変更を行った。(割り振りの変更等を行った音訓及び付表の語は,表中において下線により示している。)
3.文部科学省 用事用語例
この「文部科学省用字用語例」は,文部科学省で公用文を作成する上での参考にするため,「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号),「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)に基づき,一般に留意を要する用字用語の標準を示したものである。
4.文化庁表外漢字 字体表
〔字体表の見方〕